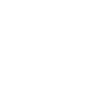Ⅰ 外部評価委員名簿
評価委員( 5 名)
| 学校法人 中部大学 工学部 兼 学術推進機構(研究戦略タスクフォース) 教授 | 黒川 卓 |
| 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 名誉リサーチャー | 清水 敏美 (委員長) |
| 台湾国立陽明交通大学 応用化学系 分子科学研究所 講座教授 | 増原 宏 |
| 国立大学法人 東京大学 物性研究所 教授 | 森 初果 |
| 株式会社 日立製作所 研究開発グループ 技師長 | 山田 真治 |
Ⅱ 外部評価資料一覧
-
外部評価資料「第6回外部評価資料」
外部評価資料の説明用スライド
スライド説明のオンデマンドムビー - 研究活動(自己点検評価報告書)
- 電子科学研究所概要(日本語版、英語版)
- 物質デバイス共同研究拠点概要
Ⅲ 評価と提言
北海道大学電子科学研究所(以下、電子研と略す)は超短波研究所の創立から77年の歴史を刻み、昨年、喜寿を迎えた。複合領域ナノサイエンス研究を推進するため、光と数理を横糸、物質と生命を縦糸とする基盤研究分野、さらには、附属グリーンナノテクノロジー研究センター、附属社会創造数学研究センター、イメージングセンターの3センターが、時代の要請を的確に掴み、機動的な組織運営を図りながら、質と量の両方が高い研究活動を推進していることは高く評価できる。以下、その前提に立って、主要な項目ごとに評価と提言を行う。
1. 組織の管理運営について
1.1. 理念、組織構成のあり方、研究領域の設定
電子研は、少人数でありながら研究者のレベルは高く、複合領域ナノサイエンスに関連する高い研究実績は世界的な注目を集めている。さらに、国、社会、企業など異なるステークホルダーに対しても電子研の認知度や期待を高めるためには、自らの強みや特色を知り、組織にふさわしいビジョンとミッションを明確に平易に伝える発信も重要と考える。
また、研究運営については、電子研が複合領域ナノサイエンスを通じてグローバルな社会課題や“北大近未来戦略150”を含む北大ミッションに対して関与、貢献していく姿勢を示すことが重要である。なぜなら、新型コロナウイルスによる災禍が重なり、多くの国民が先行きの不透明感や不安定性を実感している。さらに、国連が2015年に打ち出した「持続可能な開発目標(SDGs)」の17の目標や昨今の世界情勢を見ても貧困、食料、水、エネルギーなど喫緊な地球規模課題が数多い。
1.2. 教員人事のあり方(採用方法、人事評価方法など)
教員人事については、研究所の研究戦略に基づいて独創的なプロジェクト研究を設定し、公募により国内外に広く人材を求め、顕著な研究業績を産出する教授人事を推進している。さらに、多くの若手人材を世界の研究コミュニティ―に輩出していることは高く評価できる。今後も、物質科学や生命科学分野においては、AI駆動型科学などの融合研究等、現在、国際的に進展している学術動向にも注視しながら、戦略的な教員人事を進める必要がある。
一方、企業や海外大学とのクロスアポイントメント制度の適用を図り、北大で初めて実施にこぎつけたことは高く評価できる。クロスアポイントメントやサバティカル制度は解決すべき課題も多いが、組織活性化のために民間企業も含めて積極的に取り組んでいただきたい。
人事評価方法に関連して、教員や技術職員に対する業績評価プロセスに面談を取り入れ、さらに研究、教育、管理運営と多面的な評価項目を導入した新しい業績評価制度は評価の透明性、客観性、納得性を高めた点で意義深い。産学連携や社会貢献の強化に向けては、研究者の動機付けとなる評価基準を柔軟かつ適切に見直すことも重要である。参考までに、企業ではPDCAをうまく回す可能性があることから目標設定の面談機会を設けることが標準となりつつある。
1.3. 人員構成(若手/女性/外国人の比率、流動性、運営の継続性等)
人材のダイバーシティーを実現することは、研究を活性化する上でも大変重要である。特に研究室トップの更なる意識改革、研究や生活環境の整備、継続的な支援及び次世代育成が必要である。さらに、技術職員による技術開発および管理維持の貢献は必須であり、組織構成及び業務管理方法を見直したことは高く評価できる。全学的な課題として、部局から本部への提案も含まれると思うが、先端的技術を有する技術職員の育成、業績に見合った給与体系、キャリアパスの形成に配慮することは重要である。
人員構成を含む組織運営については、将来構想検討委員会が果たす役割は非常に重要である。今後も電子研が先陣を切って種々の新機軸を試行し、全学に展開する若々しい組織であり続けるためにも活発な活動を期待したい。例えば、電子研のあるべき姿が人材起点かミッション起点なのか、それに相応しい組織構成はどうあるべきかなどを議論することは意義がある。
2. 研究活動について
2.1. 学術論文
平成28年度~令和元年度における総論文数の推移において国際共著論文比率が最近では50%近い値に達していることは研究活動の国際化の観点から高い注目に値する。科学技術・学術政策研究所の調査資料「科学研究のベンチマーキング2019」によれば、日本の自然科学系の論文における国際共著率(2015―2017年)が32.9%であることから高い水準であると評価できる。さらに、論文学術誌のTop10%論文数の推移においては、2019年に達成した15%前後の今後の数値の維持に期待したい。
2.2. 予算の獲得状況(科研費等競争的資金、企業からの共同研究資金)
予算の獲得状況の中で、平成27年からのJST戦略的創造研究推進事業(さきがけ)9件の獲得は研究者の一つのキャリアパス(例えば、さきがけ→CREST→ERATO→A-STEPなど)の出発点を提供する意味で重要である。さらに、それら個人研究が、さらなる創造的な研究の推進、他分野や他研究者との協働、共同的色彩の強い競争的な外部資金の獲得などにつながる可能性を秘めており、高い評価にふさわしい事例と言える。
2.3. 共同研究拠点や研究プロジェクトの実施状況
共同研究拠点の実施状況については、5研究所のアライアンス網で相互に連結させ、しかも、その一端を台湾へ橋架けしたネットワーク型ハブ・アンド・スポーク共同研究システムを実践している点で高く評価できる。特に、若手研究人材の育成や人材流動の促進も念頭に入れた体制は注目に値する。言い換えれば、この共同研究体制は第6期科学技術基本計画で議論が進んでいる大学発の新たな社会改革を先導するシステムと強く言える。さらに、基盤を支える5附置研究所の200人弱に及ぶ技術職員の持続的な技術力向上とモチベーションの維持向上を図り、技術専門人材の育成に関して国内の模範となっていることも高く評価できる。
さらに、Core-to-Core Programの研究拠点形成事業は先端的な研究拠点事業を世界展開した研究プロジェクトとして注目できる。北大初の海外大学とのクロスアポイントメントを連携基盤とする電子研教授の尽力、さらに電子研の国際連携推進室や北大国際部による深いサポート体制の結実として採択に至っている。この経緯と経験は、台湾、ベルギー、オーストラリアなどの海外ネットワークに引き続いて、更なるメリハリをつけた拡充に大きな励みになることを期待したい。
2.4. 機器共用化推進や研究支援体制強化
機器共用化推進に関連して、上述したネットワーク型共同研究拠点の形成は高く評価できる。その理由として、「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」(令和2年1月、総合科学技術・イノベーション会議)の中で謳われている若手研究人材の環境改革(研究設備・機器の整備・共用化の促進)を先導する具体的な規範と模範を提示している点が挙げられる。今後は、数ある共同研究成果の中で特筆すべき成果を効果的に発信していくことも重要と考える。
また、若手研究人材については、第6回外部評価資料の約60箇所、随所に“若手”の用語が見られ、電子研が若手研究人材の発掘、育成、支援を強く意識していることを物語っている。特に若手研究人材の研究と教育の国際化を強く意識した台湾国立陽明交通大学理学院との共同研究教育センターの設立や研究拠点形成事業(Core-to-Core Program)の推進は高く評価できる。これらの取り組みは海外共著論文率が34%(H28)、50%(H29)、54%(H30)と高い数値の証左となっている。
3. 国際化の取り組みについて
3.1. 国際化の取り組み(全般)
国際共同研究、国際共同教育は世界中の大学の何十年来の課題であり、米国、欧州では早くから進められてきた。文化や言語に多様性があるアジアでは、乗り越えるべき問題も多いが、シンガポール、韓国、香港では、大胆な試みもなされてきた。このような流れの中で、電子研は、共同教育センター、国際研究拠点形成事業、Hokkaido Summer Institute、STSIプログラムなど、独特な試みを地道に実践してきている。単に多くの交流協定を結ぶのではなく、選択と集中によるメリハリをつけた国際化に取り組んでいる姿勢は評価できる。ダブルアポイントメント、クロスアポイントメント、そしてダブルファンディングこそが、言語、習慣、文化の差を超越したボーダーレスの研究活動を展開する、真の国際化につながる道である。ぜひ「海外クロスアポイントメント制度」を復活してもらいたい。
3.2 台湾国立陽明交通大学理学院共同研究教育センターの設置
台湾国立陽明交通大学理学院との間で共同研究教育センターを設立した点は注目に値する。今後は、交流の結果としての成果がアカデミアや産業等に与えた内容についても常に発信する姿勢が重要である。一方、技術覇権問題で米中が対立する中で台湾の電子産業は両国から頼られている。台湾の電子産業は1990年ころから急激に発展して世界をリードするに至った。産業と学問は連動する。産業界のように台湾に仕事を丸投げせずに、電子科学分野における日本の研究者や学生の学習意欲を維持・向上するために台湾との交流をさらに推進すべきと考える。ただし台湾でも大学の研究者は必ずしも産業に対して興味を持たない可能性もある。北大電子研の研究を研究で終わらせず、台湾国立陽明交通大学を通じて同大学とつながりのある台湾の電子機器メーカーと連携することも必要と考える。
4. 社会連携について
4.1. 産学連携(企業との共同研究)
産学連携については、北海道発のイノベーション拠点となっている北キャンパスが部局では実行が難しい新しい企画や実践の場であり続けることは魅力であり重要である。例えば、実力のある共創研究支援部がサービスの外販を積極的にコーディネートする可能性[(国研)物材機構、(国研)産総研、道総研等との連携を含む]も検討する意義はある。また、北キャンパスのミッションの一つと考える地域産業支援に関しても敷居を低くし、例えば、地域課題や企業・自営業者の困りごとに対するワンストップサービス型の活動を展開するなど、北大本部と連携しながら検討いただきたい。
一方、大学の役割は教育と教育レベルを高める研究にあり、研究成果を産官などを介して社会実装する責任がある。企業の技術開発戦略がこの10年大きく変化し、研究開発の徹底的な効率化や自前主義からの脱却等が重視されている。言い換えれば、大学の独創的で優れた研究成果や価値に対する期待度は非常に高い。企業との出会いは“待ち”では実現せず、政治家を含む一般人に対する戦略的な広報発信活動についてさらなる議論や工夫をお願いしたい。
その他、社会連携に関連して、新たに導入したシニアによる提案書添削や客員教授による講演会を通じた助言が功を奏していることに注目したい。数年かけて、ボランティアベースのアドバイザーネットワークを構築することも一案ではないかと考える。
4.2. アウトリーチ、広報活動
広報活動については、ホームページがデザイン性も良く改善された。しかし、研究所の重要なステークホルダーは学生や保護者ばかりでなく、一般市民、技術者、研究者等である。電子研のプレゼンスをさらに高めるためにはフロントページに理念やミッション、重点取り組みなどを露出させることも重要である。なおホームページの見た目だけを工夫しても利用されなければ全く意味が無い。国内外の数限りない大学や企業がホームページを公開している中、電子研のホームページにアクセスする目的を客観的に考え、どのようにすれば利用者が増えるかを考えることが極めて重要と言える。
一方、アウトリーチ活動については、新聞社や多様なメディアを活用した小中高生を含む一般市民との科学対話(大学祭に合わせた研究所一般公開、Academic Fantasista事業、体験型科学講座、サイエンスカフェなど)の実践など、積極的な社会貢献活動は驚嘆に値する。電子研を記述した新聞記事が1992年10月から216件、第3期の2016年4月からに限定しても41件あった。さらに読売新聞社の協力を得てわかりやすいプレスリリースの書き方を訓練している点も高く評価できる。
今後は、研究をおろそかにしない程度に成果をわかりやすく社会に伝え、社会との交流を進めることは重要と言える。大学や研究所は信頼性のある科学技術を根拠とするイノベーション創出の源泉である。限られた陣容や予算で今以上に広報活動を進めるには、新型コロナウイルス禍で使用頻度が増えた、例えば、YouTube などの動画配信サービスやZoomなどのリモート会議システムを積極的に活用すべきと考える。遠隔技術を使えば研究所の立地の有利不利は無い。
5. 大学の機能強化への貢献について
5.1. 教育活動、研究力強化、学内連携
大学の機能強化に関連して、電子研は北大科学技術の牽引車、スターブランドであり、北大生の誇りであろう。しかし教員に占める北大卒業生の割合は低い。重要なキャリアパスとしての電子研という位置づけを示す客観的な証左を示すことが必要かもしれない。また、安易に北大生を優遇することはできないが、ポスドクのレベルでのインセンティブ(例1:電子研で学位を取得したら希望者に最低一年間ポスドクを保証、例2:北大の研究科から学位を取得した者をポスドクとして採用した研究室に経費の何%を補助)は可能ではないかと考える。
研究力強化については、2019年4月に文部科学省は「研究力向上改革2019」を取りまとめた。しかし、“研究力”に対する定義はなく、包括的な用語として扱われている。JST-CRDS調査報告書(CRDS-FY2019-RR-02)「異分野融合を促し、研究力向上を支える土壌を育む」では、研究力を“研究成果に到達した源泉たる力”としてとらえている。“ヒト、モノ、カネ、チエからなるインプットとしての研究資源を質と量からなる成果にどのような投資効果によって実現したか”とほぼ同義である。ネットワーク型共同研究拠点は研究力の大幅な向上を達成しているわかりやすい事例である。ネットワーク型共同研究拠点を利用した際のユーザー研究者から見た投資効果(ROI: Return on Investment)(言い換えれば、研究力強化)を若手研究者とともに定量的に議論することも研究力の強化を訴求できる方策かも知れない。